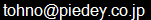|
||||||
|
私は荒れていた。 いや、10代の少女など、それが普通だったのかもしれない。 親兄弟もいなかったら、それを止める家族もいなかった。 チンピラをぶちのめした翌日に学校に呼び出しを食らい、停学を命じられた。それが学校の判断だった。 唯一の味方は担任の先生だった。 冴えない男の先生は、私に非はないといい、残念そうな顔をした。 「いえ、分かっています」私は堪えた。「幸せな娘なら戦わない筈だと思います」 「でも、強さは君の君らしい美徳だ」と先生は言った。「どうだい、これに応募してみては」 先生が出したチラシには、美少女戦隊ガールズ5欠員募集と書いてあった。 「なんですか? 見世物ですか?」 「いや、正義の味方だ」 「マジで?」 「そうか。君はまだ知らないのだね」 「何を?」 「ジャッカーという悪の組織が暗躍している。政府は、表だって対抗するとパニックになるから、秘匿性の高い対抗チームを組織したわけだ」 「まさか」 「今となっては、国民の3割は知っていると言われている」 結局私は半信半疑で面接に出た。唯一の味方である担任の勧めだったからだ。 そこで行われたのは実戦さながらの格闘試験だった。本当に強い教官と先輩にあっさりとひねられた。だが、意外にもそれで合格した。時間いっぱいまで諦めなかったガッツが認められたらしい。 「今日から君はガッツウィングだ」 私は真っ赤な強化スーツを受け取った。 ガールズ5のメンバーになった私は毎日を戦いに捧げた。それが平和のためだった。仲間の境遇も私とほとんど同じだったから、負い目は感じなかった。ガールズ5に入らなければ、きっと人生を踏み外していただろう。 半年ぐらいで、電撃隊を自称するジャッカーの怪人軍団はほぼ壊滅し、ジャッカーの幹部が自ら出てくるケースが増えた。 中でも強敵はプロフェッサーと呼ばれる死神だった。次々と新兵器を発明する才能は悪魔的だった。 プロフェッサーは、ジャッカーバルカンという新兵器を実験するために都心に出てきたので、それを察知したガールズ5と激闘になった。やっと発射を阻止してカウントを見ると、なんと2だった。ぎりぎりでガールズ5の勝利だったので、肝を冷やした。プロフェッサーは左腕を負傷して、ジャッカーバルカンを諦めて退却した。 その後で私は何食わぬ顔で登校した。ガールズ5のメンバーであることは秘匿されているからだ。 しかし、驚いたことに担任も左腕を怪我していた。 「階段で転んじゃってさ。ははは」 夜、イカを肴にビールを飲みながら担任は笑った。 だが、私には分かってしまった。担任がプロフェッサーで間違いない。 私は決定的な証拠を求めてガールズ5の研究部門を訪問した。そこで、個人識別用の液体の試作品をもらった。目には見えないが、相手の体に付着させておくと、特殊な光線で光るのだ。 私は、うっかり転んだふりをして液体を担任に掛けた。 そして、ついにプロフェッサーとの決戦を迎えた。 「攻撃は待ってください」と私はリーダーに願った。 「どうして?」 「あれは、私の担任の先生なんです」 「どういうこと?」 「分かりません。でも証明はできます」 「どうやって?」 「あらかじめ、先生に特殊な液体を掛けておきました。このライトを当てると光るはずです」 私は特殊ライトをプロフェッサーに当てた。 液体を掛けた部分が光った。 「なるほどね」 「そうか、正体がばれてしまったのか」プロフェッサーもがっくりと膝を突いた。 「教えてください。なぜですか。なぜジャッカーなんていう悪の組織に寝返ったんですか?」 「寝返ったわけではない」 「え?」 「僕らは、みな、危うい子供を抱えて困っていたんだ。そこで、有り余る若い力を健全に発揮できる場を用意したんだ」 「それがジャッカー?」 「いや、ガールズ5さ」 「まさか」 「でも、そうそう都合良くガールズ5が戦う相手はいなかった。本当の巨悪は君たちで戦えるような相手ではないしね。それでは意味がないので、僕らが自分で敵になったというわけさ」 「まさか、ジャッカーの他の幹部も」 「みんな、君たちの大事な人の変装さ」 (遠野秋彦・作 ©2010 TOHNO, Akihiko) |
|
||
|
|